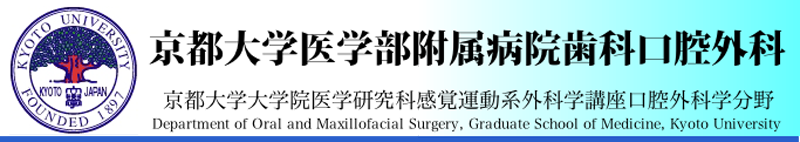先端高度医療として、臓器移植が医療としてほぼ定着し、軟骨や皮膚などの組織再生が臨床応用され始めている。さらに今後21世紀に、最も期待される分野が器官再生である。われわれ歯科口腔外科領域においても、組織工学的な手法を用いた歯牙再生の試みが報告されはじめきている。先日ヒトゲノムドラフト配列が公開され、ポストゲノム研究としてゲノムワイドな疾患遺伝子解析が開始されはじめ、その膨大な遺伝子情報に基づく医療というものが新たに展開されることになるであろう。そこで、他科領域においては、すでに心臓再生、血管再生などが活発に遺伝子レベルで研究されはじめており、我々歯科口腔外科領域においても歯牙の再生を目的に遺伝子レベルで解析することは、重要なテーマと考えられる。
歯牙は、上皮間葉相互作用により形成され、歯間葉細胞は、多分化能を有する頭部神経堤細胞由来であることが知られている。その分子機構について解析が進められ複雑な分子ネットワークの存在が明らかにされてきた。一方、爬虫類以下は多生歯性であるのに対し、ヒトでは、大臼歯が一生歯性以外は二生歯性で、歯数は厳密に制御されているが、その分子メカニズムは明らかでない。近年、歯数が増加するノックアウトマウス(USAG-1)やトランスジェニックマウス(LEF1,EDA,EDA-R)や遺伝性に過剰歯を起こす遺伝子変異(RUNX2)など、1つの遺伝子の発現量、遺伝子変異で歯数が増加することが報告され、1つの遺伝子により歯数を増やすことのできる可能性が示唆されてきた。
我々のグループでは、その蓄積された基礎的知識をもとに、歯牙形成過程において、特に歯数の制御に着目し、USAG-1欠損マウスなどのモデルマウスやRUNX2などの候補遺伝子の組み換えウイルスを第一鰓弓や歯胚の器官培養に強制発現させる実験系を用いて、歯数を制御するメカニズムを遺伝子レベルで明らかにすべく解析を行っている。将来的には、その分子メカニズムを利用してin vivoで歯胚の数を増加させるシステムを確立することを目指している。
歯牙再生グループ
歯牙再生グループ